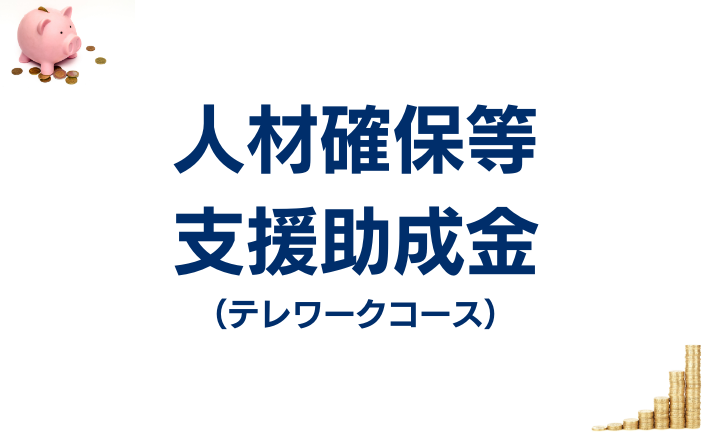テレワークの導入は、労働者の働き方に大きな変革をもたらすだけでなく、企業にとっても重要な戦略の一つとなっています。とくに、中小企業にとっては、適切な支援を受けることで、テレワーク導入の負担を軽減し、労働環境の改善や人材確保にもつなげることが可能です。
本記事では、人材確保等支援助成金(テレワークコース)についての基本的な情報から申請手順までを詳しく解説します。ぜひご参考ください。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)ついて
人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、中小企業がテレワークの導入や運用を支援するための助成金です。労働者の生活の質を高め、ワークライフバランスを向上させながら、企業の雇用管理や労働環境の改善を図ることが目的です。この助成金は、テレワークに必要な機器の導入や運用にかかる経費に対して支給され、最終的に効果を出した場合には追加の助成が支給されます。
対象企業
この助成金の対象となるのは、中小企業事業主です。とくにテレワークを新規導入する企業や、既に導入しているテレワークを拡大する企業が主な対象です。業種に関わらず、テレワークの推進を目指している企業であれば申請することが可能です。また企業トップからのメッセージ発信など、テレワークの職場風土づくりに積極的に取り組む事業主が求められています。
申請基準
助成金を受給するためには、まずテレワーク実施計画を策定し、管轄の労働局へ提出して認定を受ける必要があります。その後、計画にもとづいてテレワークを実施し、評価期間中に対象労働者全員が週平均1回以上テレワークを行うなどの基準を満たすことが求められます。またテレワーク促進のために企業トップの発信や、職場環境の整備も重要な要件です。これにより、テレワークが定着しやすい環境が整うことが条件となります。
機器等導入助成においては評価期間(3カ月)に、在宅またはサテライトオフィスでのテレワークを実施することが必要です。その間に達成すべき目標は以下の2つです。
| ・評価期間に1回以上、対象労働者全員に終日在宅で就業するテレワークを実施すること ・対象労働者が終日在宅でテレワークを実施した日数の週間平均を1回以上とすること |
目標達成助成における、離職率目標は以下の2つです。
| ・計画期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること ・計画期間後1年間の離職率が30%以下、または評価期間の前後でテレワーク率が向上していること |
給付金額
この助成金は、機器等導入助成と目標達成助成の2段階で支給されます。機器等導入助成では、支給対象となる経費の50%が支給され、1企業あたり100万円またはテレワーク実施対象労働者1人あたり20万円が上限です。目標達成助成では、離職率の低下やテレワークの定着などの目標を達成した場合、支給対象経費の15%が支給され、賃金要件を満たす場合は25%に引き上げられます。こちらも1企業あたり100万円が上限です。
もっと詳しく知りたい方
出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(テレワークコース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)」
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の申請手順
人材確保等支援助成金(テレワークコース)の申請手順については、以下の通りです。
- テレワーク実施計画の作成
- 計画の実施
- 助成金の申請
- 目標達成後の申請
- 助成金の受け取り
この手順に従い、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)を効果的に活用することで、企業の労働環境をより良い方向へ進めることができます。
まずはテレワーク導入に関する実施計画を作成し、管轄の労働局に提出します。計画には、具体的なテレワーク導入の方法や目標が含まれている必要があります。
計画が認定されると、実際にテレワークを導入し、労働者が週1回以上テレワークを行うことが求められます。
テレワーク導入後、実施状況を評価し、評価期間が終了した段階で助成金の申請を行います。申請には、導入した機器やツール、研修の実施状況などを証明する書類が必要です。
離職率の低下やテレワークの定着など、目標を達成した場合には、目標達成助成の申請を行います。こちらも、証明書類を添付して提出します。
労働局から助成金が支給され、企業の口座に入金されます。これで助成金の手続きが完了します。
まとめ
人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、テレワークの導入や拡大を目指す中小企業にとって強力な支援策です。労働者の働きやすい環境を整備することで、企業の競争力を高め、離職率の低下や人材確保につながります。適切な計画と実施を通じて、助成金を最大限に活用し、柔軟な働き方を実現しましょう。この記事で紹介したポイントを参考に、テレワーク導入を一歩進めるきっかけにしていただければ幸いです。
そして、みなさんも健康経営のサポーターとして、健康経営を実践していきましょう。健康経営に挑戦したい方や健康経営の進め方に悩まれている方は、ぜひ「本橋柊」までお問い合わせください。
\ 一緒に健康経営に挑戦する! /