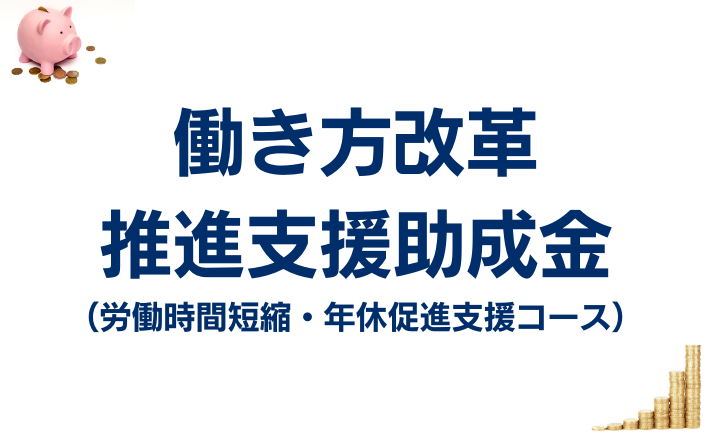企業の健康経営に向けた支援として、労働時間短縮や特別休暇の促進を行う中小企業を対象にした助成金があります。この助成金を活用することで、働き方改革を推進し、従業員の健康を守りながら生産性の向上を図ることが可能です。
本記記事では、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の基本的な情報から申請手順について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)ついて
この助成金は、労働時間の短縮や年次有給休暇の計画的付与、特別休暇制度の導入など、従業員の健康を考慮した環境整備に取り組む中小企業事業主を対象に支給されます。とくに、36協定の時間外労働時間数を月60時間以下に縮減するなど、具体的な目標達成に対して経費の一部が助成される仕組みです。また賃金引き上げを行う場合には、さらに助成金額が加算される仕組みが特徴的です。
対象企業
この助成金の対象となるのは中小企業であり、業種や規模に応じて条件が異なります。一般的には、資本金が3億円以下であり、常時雇用する従業員数が300人以下の事業者が対象となります。また、労働者災害補償保険の適用を受けている企業であることが必須条件です。飲食業やサービス業、卸売業、小売業など幅広い業種が対象となりますが、企業の規模や従業員数に基づいた条件を満たす必要があります。
申請基準
助成金を申請するには、いくつかの基準を満たす必要があります。まず、36協定に基づく時間外労働時間の縮減を含む成果目標を設定し、その達成を目指すことが必要です。具体的には、時間外労働を月60時間以下にすることや年次有給休暇の計画的付与、特別休暇制度の導入などが挙げられます。また、すべての事業場で年5日の年次有給休暇取得のために就業規則を整備することも求められます。
給付金額
助成金の給付金額は、実施した取り組みや達成した目標に応じて異なります。36協定に基づく時間外労働時間数の縮減では、最大で200万円が支給され、年次有給休暇の計画的付与制度の導入には最大で50万円が支給されます。また、特別休暇制度の導入や賃金引き上げによる加算があり、賃金引き上げ人数に応じて15万円から最大240万円の加算が得らることが可能です。全体の助成額は、取り組みの数や規模により異なりますが、最大で490万円の助成金が支給される可能性があります。
もっと詳しく知りたい方
出典:厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)」
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の申請手順
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の申請手順については、以下の通りです。
- 計画の策定
- 必要書類の準備
- 申請書類の提出
- 計画の実行
- 取り組みの報告
- 助成金の受給
この手順に従うことで、働き方改革推進支援助成金を受給することができます。
まず企業は、自社の現状を踏まえた計画を策定します。36協定の変更、労働時間の短縮、年次有給休暇の付与、特別休暇制度の導入などの具体的な目標を決めます。また賃金引き上げを行う場合には、その計画も含めます。
計画が決まったら、助成金の申請に必要な書類を準備します。主に以下の書類が必要です。
- 就業規則や労使協定の改定案
- 36協定の変更案(労働時間短縮の目標がある場合)
- 賃金引き上げの証拠書類(該当する場合)
準備した書類を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出します。書類の提出は、窓口への持参または郵送で受け付けられます。提出後は審査が行われます。
労働局から申請が承認された後、計画にもとづいて取り組みを実施します。例えば、36協定の変更や年次有給休暇の付与、労務管理ソフトの導入、外部専門家によるコンサルティングの実施などです。取り組みの内容は、助成金の対象となる活動に沿ったものである必要があります。
計画の実施が完了したら、取り組みの成果を報告します。このとき、必要な書類を再度労働局に提出します。例えば、労働時間の短縮が実現したことや特別休暇制度が導入されたことを証明する書類を提出します。
報告が受理され、審査を通過すると助成金が企業に支給されます。支給額は、達成した成果目標や実施した取り組みに応じて決定されます。
まとめ
健康経営を支援する助成金は、従業員の働きやすい環境を整備するために非常に有効です。労働時間の短縮や年次有給休暇の付与、特別休暇制度の導入など、企業の取り組みが成果に結びつけば、経費の一部が助成されます。また、賃金引き上げに対する加算もあるため、企業としての取り組みが従業員のモチベーションアップにもつながります。制度をうまく活用し、働き方改革を推進していきましょう。
そして、みなさんも健康経営のサポーターとして、健康経営を実践していきましょう。健康経営に挑戦したい方や健康経営の進め方に悩まれている方は、ぜひ「本橋柊」までお問い合わせください。
\ 一緒に健康経営に挑戦する! /